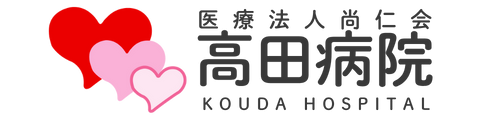適切な意思決定支援に関する指針
第1章 趣旨
本指針は、患者の意思を尊重した医療の提供を実現するため、当院における意思決定支援の基本的な考え方、体制および運用方針を定めるものである。この指針は、厚生労働省通知(令和6年3月5日付 医政発0305第1号)に基づき、患者本人の意思を最大限尊重し、適切な情報提供と支援を行うことを目的とする。
第2章 基本的考え方
1.患者の治療方針・療養方法の選択にあたっては、本人の意思を最優先する。
2.患者が意思を表明できない場合には、家族や代理人の意向、ならびにこれまでの本人の希望を尊重する。
3.医療者は十分な説明を行い、患者が理解・納得したうえで意思決定できるよう支援する。
4.強要や誘導を行わず、中立的な立場から支援を行う。
5.多様な価値観を認め、文化的・宗教的背景にも配慮する。
第3章 支援体制
1.意思決定支援は、主治医を中心に、看護師、医療ソーシャルワーカー、薬剤師、リハビリ職、管理栄養士などの多職種が連携して行う。
2.必要に応じて、倫理委員会や多職種カンファレンスを開催し、複雑な事例や意見の不一致に対して検討を行う。
3.意思決定支援の相談窓口を医療相談室に設置し、患者および家族からの相談に応じる。
第4章 意思確認と記録
1.治療方針や療養内容についての話し合いは、診療録または意思決定支援記録書に記録する。
2.記録には、説明内容、患者の理解度、同席者、合意内容を明確に記載する。
3.病状変化や本人の意思変更時には、再度説明・協議を行い、記録を更新する。
4.記録は診療録と同等の期間保存し、医事課が管理責任を負う。
第5章 教育および職員研修
1.年1回以上、意思決定支援に関する研修を実施し、患者中心の医療の理念を職員に周知する。
2.研修には、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)や倫理的課題に関する内容を含める。
3.新任職員には入職時研修において意思決定支援の基本を教育する。
4.研修記録は開催日時・内容・出席者を記録し、3年間保存する。
第6章 倫理的対応
1.患者・家族・医療者間で意見の不一致や倫理的課題が生じた場合は、倫理委員会で協議する。
2.倫理委員会は、医師、看護師、ソーシャルワーカー、外部委員等で構成し、客観的かつ公正な助言を行う。
3.緊急時に委員会を開催できない場合は、管理者・看護部長・医療相談室長により暫定対応を行い、後日倫理委員会で検証する。
第7章 公開および周知
1.本指針の存在を院内掲示等で周知し、患者および家族が閲覧できるようにする。
2.本指針の全文は、医療相談室または病棟スタッフステーションで閲覧可能とする。
3.職員には年1回の研修およびイントラネット・掲示等を通じて周知を行う。
第8章 見直し
1.本指針は、診療報酬改定、社会的情勢の変化、または院内体制の変更に応じて、年1回を目安に見直す。
2.改訂は管理者が承認し、倫理委員会で報告・周知する。
第9章 「人生の最終段階における医療・ケアの意思決定に関する指針」との関係
本指針は、当院におけるすべての入院患者を対象とした包括的な意思決定支援体制を示すものである。
「人生の最終段階における医療・ケアの意思決定に関する指針」は、本指針の理念を踏まえ、終末期医療等の特定領域における意思決定支援をより具体的に定めたものである。
したがって、両者は相互に補完関係にあり、患者の状態や医療状況に応じて併用する。
附 則
(施行期日)
本指針は令和6年4月1日から施行する。
(改訂履歴)
令和6年4月1日 制定